借地権とは?種類や所有権との違い、メリットを分かりやすく解説!

借地権という言葉を耳にしたことはありますか?
借地権を一言で言えば、建物を建てるために土地代を支払って他人から土地を借りる権利のことを言います。借地権には幾つか種類や特徴があり、メリットやデメリットも様々です。今回はそんな借地権について解説していきます。

借地権とは?

「借地権」は、土地を借りて家を建てる場合に、土地を借りる権利のことを言います。土地は地主、建物は自分のものになります。借地権付きの土地を借りる場合、借主は地代を地主に払わなければなりません。そのため、建物を建設するときや立て替えるときは、地主の許可や連絡が必要となります。
また借地に建てた建物を売却するときも、地主の承諾が必要になります。借地には、契約期間があるので注意が必要です。
「借地権」と「所有権」の違い
借地権と所有権の最も大きな違いは、土地に対する権利の強さと自由度です。所有権が土地を完全に自分のものとして自由に利用、処分できる絶対的な権利であるのに対し、借地権はあくまで「借りている」権利であるため、様々な制約が伴います。
| 比較項目 | 借地権 | 所有権 |
| 土地の所有者 | 地主 | 自分自身 |
| 土地の利用 | 建物の所有目的に限定される | 原則自由 |
| 増改築・売却 | 地主の承諾が原則必要 | 自由に行える |
| 固定資産税等 | 土地分は不要(建物分は必要) | 土地・建物両方に必要 |
| 地代 | 毎月支払う必要がある | 不要 |
このように、借地権は所有権に比べて費用面での初期負担が軽い一方で、長期的な地代の支払いや利用の自由度に制限があることを理解しておく必要があります。
「地上権」と「賃借権」の違い
借地権は、その法的な性質によって「地上権」と「土地の賃借権(賃借権)」の2種類に大別されます。
地上権は、他人の土地を直接的に支配できる強力な権利(物権)です。そのため、地主の承諾がなくても、借地権を第三者に譲渡したり、土地を転貸(またがし)したりすることが可能です。また、登記が義務付けられています。
一方、賃借権は、地主に対して「土地を使わせてほしい」と請求できる権利(債権)です。地上権に比べて権利が弱く、借地権の譲渡や転貸には原則として地主の承諾が必要です。登記も義務ではありません。
現在の借地契約のほとんどは、地主の権利がより保護される「賃借権」が設定されています。 そのため、一般的に「借地権」という場合、この「賃借権」を指していることが多いです。
借地権の種類について

借地権と一言でいっても、その契約がいつ結ばれたかによって適用される法律が異なり、権利の内容も大きく変わってきます。具体的には、1992年8月1日に施行された「借地借家法」を境に、「旧法借地権」と「新法借地権」に分けられます。
そして、旧法・新法にかかわらず、この借地借家法で規定される「借地権」とは、建物所有を目的とした土地を借りる権利とされています。
一方で、建物所有を目的としない土地の賃貸借とはどんなものか?例として、月極駐車場や資材置き場としての土地賃貸借などが挙げられます。これら場合、以下に述べるような借地借家法の適用はなく、存続期間や解約条件などを自由に定めることができます。
旧借地権(旧法)
旧借地権は、現在の借地借家法が制定される以前の法律が適用される借地権のことを言います。1992年7月31日までに契約が成立していたものは、旧借地権が適用されます。旧借地権は、堅固建物と非堅固建物で契約の存続期間が別に定められています。
木造などでは30年、鉄骨造などでは60年が期間です。賃借権は更新することができますが、貸主の側から契約の更新を拒否する場合は、正当な理由が必要です。
| 建物の構造 | 当初の存続期間 | 更新後の存続期間 |
| 堅固建物(鉄筋コンクリート造など) | 30年以上(定めがない場合は60年) | 30年以上(定めがない場合は30年) |
| 非堅固建物(木造など) | 20年以上(定めがない場合は30年) | 20年以上(定めがない場合は20年) |
参照:借地借家法
普通借地権(新法)
地主側の権利が弱すぎた旧法の問題点を解消し、土地の有効活用を促進するために、1992年8月1日に「借地借家法(新法)」が施行されました。これ以降に設定された借地権が「新法借地権」です。 新法借地権のうち、契約の更新が可能なタイプを「普通借地権」と呼びます。
旧借地法に基づく借地権との最も大きな変更点は存続期間です。初めの存続期間は構造に関わらず最低30年で、1回目の契約更新は20年以上、2回目以降は10年以上で設定します。
| 契約のタイミング | 存続期間 |
| 当初の契約 | 30年以上 |
| 1回目の更新 | 20年以上 |
| 2回目以降の更新 | 10年以上 |
定期借地権(新法)
定期借地権は、更新がなく、契約期間経過後に終了する借地権です。
これにより、地主は将来的に土地が確実に返還されるという見通しを持って、安心して土地を貸し出すことができるようになりました。
一般定期借地権(=建物の使用目的に制限なし)は更新がない代わりに存続期間が50年以上と長期になります。
また、定期借地権には、主に以下の3つの種類があります。
- 一般定期借地権: 存続期間を50年以上とし、契約終了後は借地人が建物を解体して更地で土地を返還します。居住用の建物に利用されることが多く、契約の更新や建物の買取請求はできません。
- 事業用定期借地権: 店舗や商業施設など、事業用の建物を目的とするもので、存続期間は10年以上50年未満です。契約終了後は同様に更地にして返還します。
- 建物譲渡特約付借地権: 契約から30年以上が経過した日に、地主が建物を買い取ることをあらかじめ約束しておく借地権です。
| 種類 | 主な内容・特徴 | 契約更新 | 存続期間 | 契約終了時の対応 |
| 普通借地権 | 旧借地法をベースに1992年の借地借家法で改正。更新が可能で、居住用・事業用どちらにも利用される。 | あり | 当初:30年以上1回目更新:20年以上2回目以降:10年以上 | 建物をそのまま使用継続可(更新時) |
| 一般定期借地権 | 更新なし。主に居住用。契約終了後は建物を解体して更地で返還。 | なし | 50年以上 | 更地にして返還 |
| 事業用定期借地権 | 商業施設・店舗など事業用に限定。 | なし | 10年以上50年未満 | 更地にして返還 |
| 建物譲渡特約付借地権 | 契約から30年以上経過した日に地主が建物を買い取ることをあらかじめ約束。 | なし | 30年以上 | 地主が建物を買い取る |
借地権付き物件のメリット
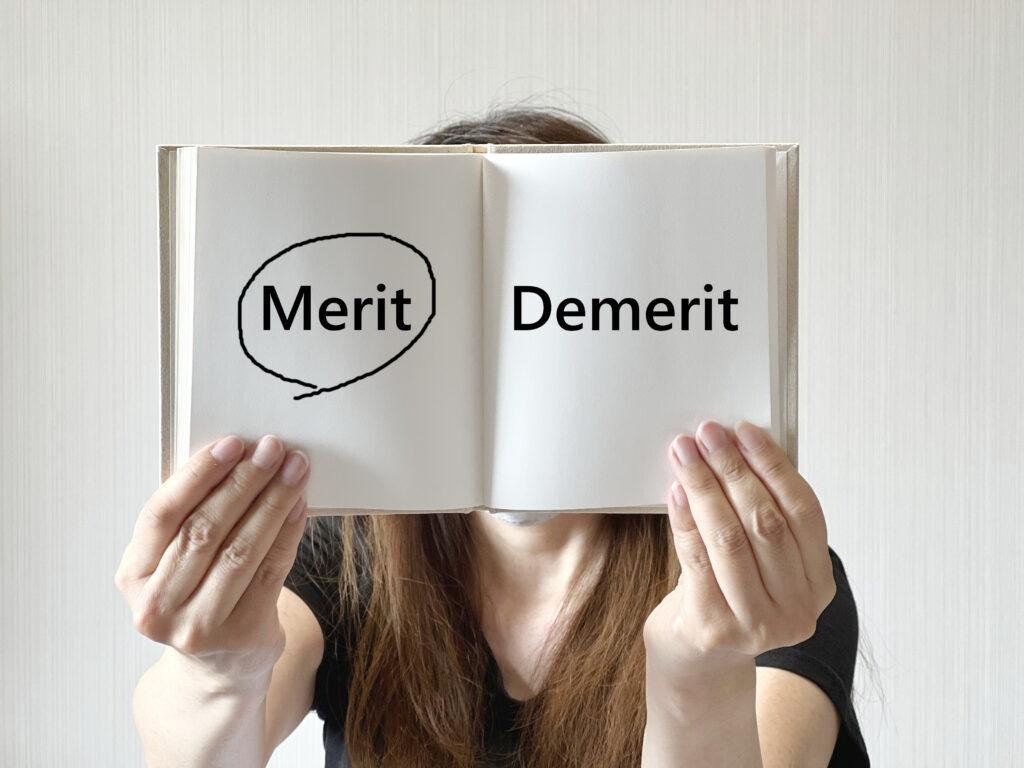
借地権付きの物件には、次のようなメリットが存在します。
固定資産税・都市計画税がかからない
土地部分に固定資産税・都市計画税がかからないのがメリットの一つです。土地を借りる権利を所有しているだけの借地人には、土地部分の課税義務が発生しません。借地であっても建物は固定資産税・都市計画税等、の税金がかかりますので注意しましょう(建物の所有者は自分になるため)。
長期間借りられる可能性がある
借地権は、存続期間が10年以上で設定されています。いずれは返さないといけないのですが、土地の所有者側に延長を拒否する正当な理由がなければ、契約は延長されるので、長期間借りることもできます。
購入時の費用を抑えられる
地域などで異なりますが、借地権付き建物の土地の価格は、同じ土地の所有権を得るのに比べ60%〜80%程度に抑えられます。都心や駅前などの地価が高い人気エリアの物件を相場以下で購入できることもあります。
借地権付き物件のデメリット
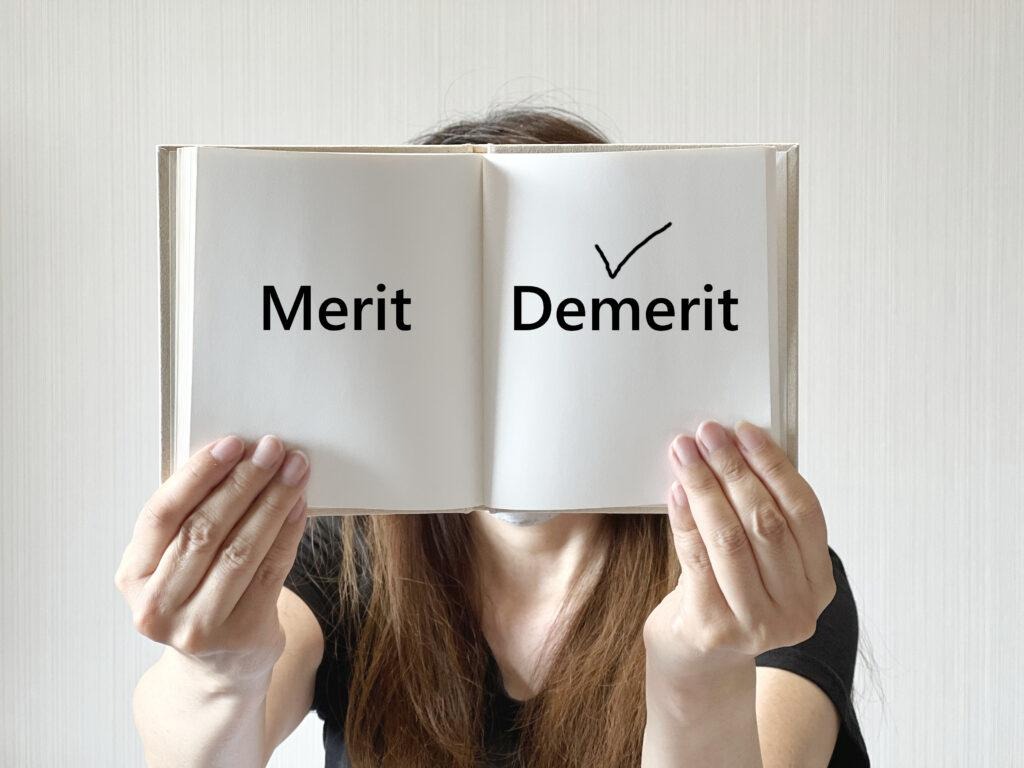
次に、借地権のデメリットについてご紹介します。
銀行からの融資が受けづらい
不動産購入は多くの場合、金融機関から融資を受けます。購入する土地や建物を担保にして融資を受けますが、土地の所有者は別にいるという点から、担保としての価値が低くなり、思うように融資を受けられないこともあります。
土地の所有者ではないので自由度が低い
借地権付き建物に関しては、借主が自由に売却したり、増改築や建て替えたりをすることはできません。土地の所有権が地主のものなので、事前に地主の承諾を得なくてはいけません。地主から許可を得ることで売却や建て替えはできますが、「増改築承諾料」や「名義書換料(譲渡承諾料)」といった承諾料が必要なケースもあるので注意しましょう。
地代がかかる
借地権は毎月地代が発生します。払い続けることに抵抗を感じる場合はデメリットに感じることでしょう。また、需要増加や都市開発などにより土地の価値が上がると、地代が値上がりすることもあるので注意しましょう。
このように、借地権にはメリット・デメリットがあります。
借地権でもいくつかの種類があり、それぞれに条件も変わりますので、借地権付き建物を購入する際には自分たちのライフプランに合わせて考えることが必要になります。
借地権付きの物件を購入する際の注意点

借地権の物件を購入する際の注意点をまとめると、以下のポイントが重要です。
借地契約の種類を確認する
借地権にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や条件が異なるため、自分のライフプランや目的に合った借地契約を選ぶことが重要です。
特に、定期借地権では更新ができないため、長期的な居住を望む場合には注意が必要です。
契約期間と更新料・地代を確認する
契約の種類によって、契約期間や更新の可否、終了時の取り扱いが大きく異なります。
また、契約更新時に「更新料」が発生する場合もあります。これらの費用がどの程度かかるのか、契約書をよく確認しておきましょう。
借地権についてよくある質問
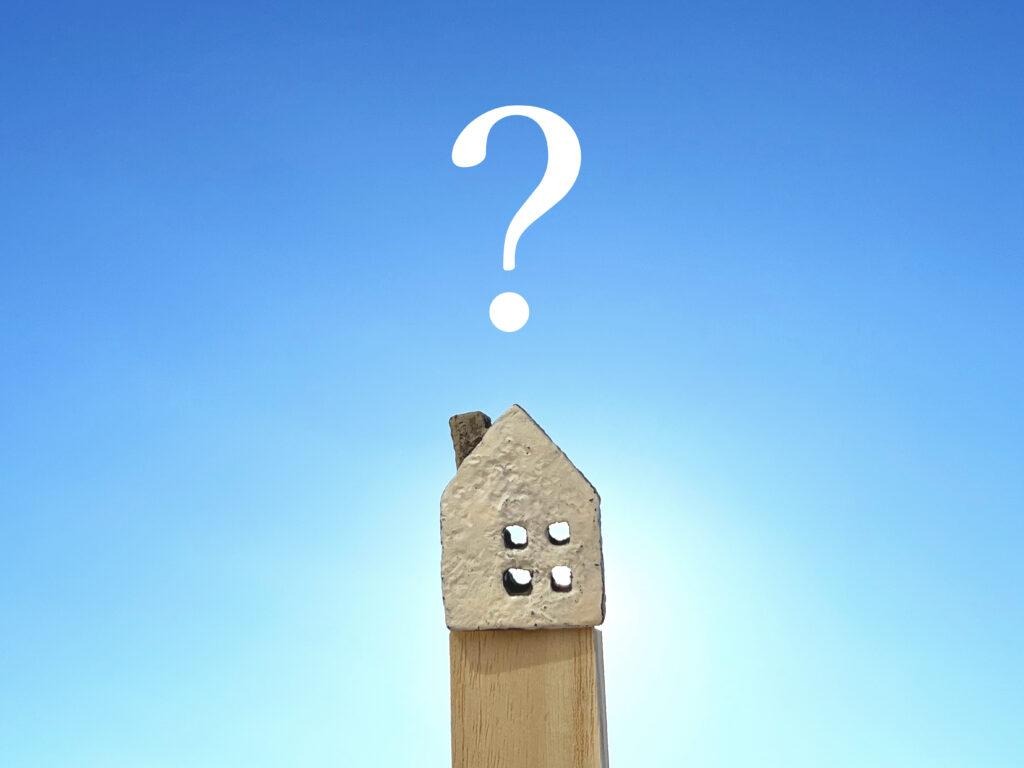
借地権に関するよくある質問をご紹介します。
借地権は売買できますか?
借地権は売買可能ですが、地主の承諾が必要であり、承諾料や名義変更などの手続きが伴います。売買にあたっては、契約内容や費用について十分に確認し、地主としっかり協議することが重要です。
借地権は相続できますか?
借地権は法定相続人であれば相続することが可能で、地主の承諾を得る必要はありません。ただし、相続後の名義変更手続きや相続税の支払いが必要な場合があります。
遺言があれば、それに従い法定相続人以外の人が相続することも可能です。遺留分や相続放棄などの特例を含め、相続の状況に応じた手続きが求められます。
まとめ

いかがでしたでしょうか。借地権はあくまで土地の所有者である地主へ地代を支払うことで利用できる権利で、それらにはいくつかの種類とメリット、デメリットが存在します。
借地権付きの建物を検討することは、住まい探しの選択の幅を広げることになります。
また、借地権の売買や相続には、上記のように専門的な知識が求められます。
愛知・静岡の地域情報に精通したサーラ不動産は、不動産のプロフェッショナルとしてお客様一人ひとりに寄り添いサポートします。借地権に関するお悩みも、ぜひお気軽にご相談ください。

■監修_サーラ不動産/担当者_資格:宅地建物取引士












