ブラインドとカーテンならどっち?費用・機能・部屋別の選び方を解説

窓まわりのインテリアを見直すときに悩むのが、「カーテンとブラインドのどっちがいいんだろう?」という点ではないでしょうか。見た目の印象が変わるのはもちろん、機能性や費用も変わってくるので、何を優先すべきなのかも悩むポイントだと思います。
そこで本記事では、ブラインドとカーテンの種類と特徴をはじめ、それぞれのメリットとデメリットを比較していきます。
部屋別の選び方も説明しますので、ぜひ参考にしてください。
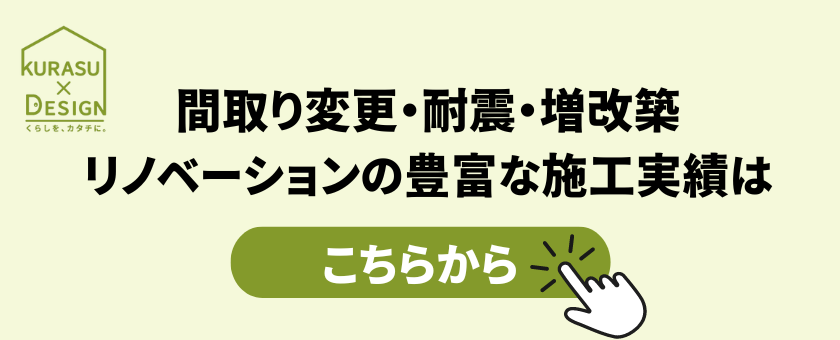
目次
ブラインドとカーテンの違い

直線的でシャープなデザインが特徴のブラインドと、布の柔らかさや華やかさが特徴のカーテン。それぞれ形状や素材がまったく異なります。
まずは、ブラインドとカーテンの種類と特徴を頭に入れておきましょう。
ブラインドの種類と特徴
細長い羽根(スラット)が水平または垂直に並び、窓の形状に合うすっきりとしたデザインなのが特徴です。スラットの角度を変えながら、光や風の出入りを調整します。
『ブラインド』と聞くとオフィスや浴室などに取り付ける横型ブラインドをイメージするかもしれませんが、最近では縦型のスラットを上から吊り下げたファブリック製の『縦型ブラインド』が人気です。
中でも、縦に連なった羽根がスタイリッシュさを演出してくれる『バーチカルブラインド』は、リフォーム・新築問わず多くの方から選ばれています。
また、ブラインドで選べる素材には、次のようなものがあります。
| 横型ブラインド | 縦型ブラインド |
| ・PVC製(塩化ビニル) ・アルミ製 ・木製 | ・ファブリック製(布) ・PVC製(塩化ビニル) ・アルミ製 ・木製 |
素材の中でもとくに人気なのは、横型ならデザイン性が高く室内のインテリアとの調和がとりやすい、PVC製や木製。縦型ブラインドなら、柔らかさを演出できるファブリック製やPVC製です。デザイン性の高さはもちろんのこと、室内のテイストに合う素材を選べるのも、ブラインドが人気を集めている理由のひとつです。
カーテンの種類と特徴
日本の住宅では、光や風、視線をコントロールするアイテムといえば「カーテン一択」といわれるほど主流です。機能性と同時に、インテリアとしての役割も担っています。
取り付け時には窓側に視線を遮るための『レースカーテン』、室内側には遮光のために『ドレープカーテン』と、2種類を組み合わせるのが基本です。
カーテンはファブリック(布)のみですが、その中でも素材の種類がとても多く、選択肢は多岐にわたります。
- 合成繊維、再生繊維(ポリエステル、アクリル、ナイロン、レーヨンなど)
- 天然素材(綿、麻、羊毛、絹など)
素材に加えて、遮光、遮熱、遮像など機能面の種類もたくさんあります。
中でもとくに人気なのは、ポリエステル素材と遮光、または断熱を組み合わせた商品です。シワになりにくく洗濯時に伸び縮みがしにくいなど、扱いやすさがポリエステル素材が人気の理由です。
ブラインドとカーテン。メリットとデメリットは?
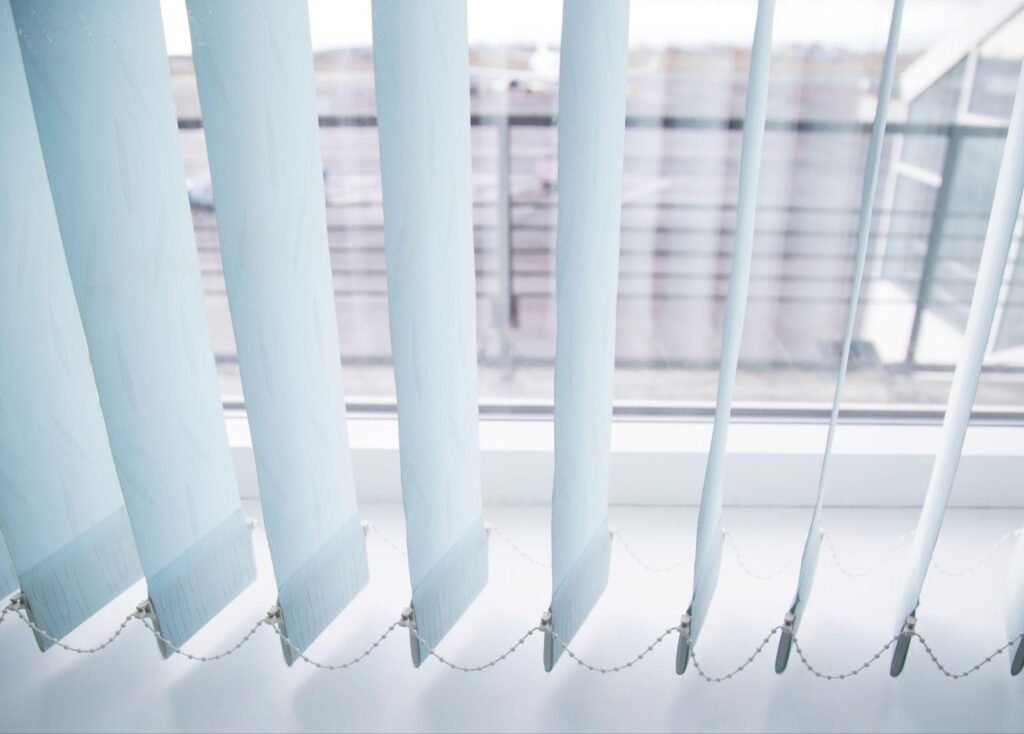
ブラインドとカーテンのどちらにするか悩んだときには、メリットとデメリットから比較してみましょう。
ブラインドのメリットとデメリット
| メリット | ・デザイン性が高く、室内がすっきりとした印象になる ・採光、通風の調整がしやすい ・調光や開閉がしやすい |
| デメリット | ・断熱性、遮音性が低い ・羽根部分にホコリが溜まりやすい(横型ブラインド) ・費用が高くなりやすい(縦型ブラインド) ・故障する可能性がある |
ブラインドのメリットは、なんといってもそのデザイン性。
窓のサイズに合うすっきりとした形状と、スタイリッシュさで部屋がすっきりとして見えます。素材しだいで、洋風・和風どちらのテイストにも合わせられます。
また、操作バトンで羽根(スラット)を動かして調光できるので、季節や天候に合わせて使い分けができるのも魅力。開閉が簡単で、羽根の角度を簡単に調整できます。
しかし、その一方で隙間が多いため、断熱性と遮音性はカーテンに劣ります。
さらに横型ブラインドは羽根部分にホコリが溜まりやすく、小まめな手入れが必須。においは付着しにくいものの、羽根を1枚ずつ拭いていくのに手間がかかります。
掃除のしやすさを優先したい方は、縦型ブラインドでなおかつ洗濯が可能なウォッシャブル対応製品を選びましょう。
そして縦・横どちらも共通で、コードの摩耗や断裂、操作バトンの不具合、羽根の折れなどの故障が起こりやすい点もデメリットです。
カーテンのメリットとデメリット
| メリット | ・遮光性、断熱性、防音性に優れている ・色柄のバリエーションが多い ・洗濯して清潔感を保てる ・簡単に取り付け、取り外しができる |
| デメリット | ・スペースを取られる ・においが付着しやすい |
カーテンのメリットは、機能面やデザインバリエーションの豊富さです。
もともと窓全体を覆うデザインのため遮光性、断熱性、防音性に優れていますが、機能性をもつ商品と組み合わせれば、さらに効果を実感できます。
ウォッシャブル対応製品が多いので、においや汚れ、ホコリが気になるときに気軽に洗濯できるのもうれしいポイント。メンテナンス次第で、10年以上使い続けられます。
また、取り付け・取り外しがしやすいので、模様替えをしたいときには気軽に交換できるのも、カーテンならではのメリットです。
しかし、カーテンを開けたときには窓の両側または片側に布がまとまるため、窓や部屋が小さく・狭く見えてしまう点はデメリット。窓際にソファやベッドなどの家具があると、もたつきが気になるかもしれません。
また、タバコやペット、調理中のにおいが付着しやすいので、消臭スプレーの利用や洗濯などのにおい対策も必須です。
ブラインドとカーテン、悩んだときの判断ポイント

メリットとデメリットだけでは決められないときには、次のポイントも参考に考えてみましょう。
デザインとインテリア性
前章で説明したように、ブラインドとカーテンとでは部屋に与える印象が大きく変わります。たとえば、スタイリッシュさやシンプルさを演出したいならブラインドが適していますが、華やかさや柔らかさなどを演出したいなら、カーテンのほうがおすすめです。
このように、ブラインドやカーテンもインテリアの一部と考えて、自分がイメージする室内のテイストに合うデザインがどちらなのかを、考えてみてください。
予算とメンテナンスコスト
ブラインドとカーテンとでは、初期費用やメンテナンスコストも変わってきます。
予算に合わせてデザインと機能性を選びたいなら、カーテンがおすすめです。高価なものだと数万円から数十万円と高額になりますが、安価なものだと数千円から数万円で購入できるので、大幅に予算オーバーしてしまう心配がありません。
ブラインドはアルミ製や樹脂製の横型ブラインドなら費用を抑えられますが、木製は高くなる傾向があります。さらに縦型ブラインド(バーチカルブラインド)はどの素材でも高額になりやすく、リフォームだと既存のレール撤去とレールの取り付け費用が別途かかる場合がほとんど。
予算に余裕がある方に向いてます。
部屋別!ブラインドとカーテンの使い分けるコツ

最後に、部屋別にブラインドとカーテンを使い分けるコツを説明します。
リビング・ダイニング
もっとも長い時間を過ごし、来客が過ごす場所でもあるリビング・ダイニングは、雰囲気づくりがとても重要です。自分好みのテイストや窓の大きさなどに合わせて、種類を選びましょう。モダンでスタイリッシュな雰囲気にしたいなら、ファブリック製の縦型ブラインド(バーチカルブラインド)や木製の横型ブラインド。温かみのある雰囲気にしたいならカーテン、といった具合に選んでみてください。
【Point!】
大きな掃き出し窓があるなら、すっきりとまとまるバーチカルブラインドがおすすめ。
縦のラインが空間をより広く見せてくれます。ただしリビング・ダイニングがキッチンとつながっている場合は、料理のにおいが移りやすいので、ウォッシャブル対応製品を選びましょう。
一方、空間にアクセントがほしいときには、柄物のカーテンを選ぶのがおすすめ。飽きたときには簡単に交換できるので、気軽に模様替えを楽しめます。
キッチン・洗面脱衣室
水や油などを使うことが多いキッチンと、湿気が溜まりやすい洗面脱衣室には、耐水性が高いアルミ、または樹脂製のブラインドがおすすめ。
スラットが汚れたときもサッと拭き取るだけで汚れが落とせるので、清潔さを保てます。
小さな窓にはカフェカーテンという選択肢もありますが、調理のにおい移りや湿気によるカビの発生リスクがあるため、小まめな洗濯を心がけましょう。
寝室・子ども部屋
睡眠の質を左右する寝室や子ども部屋には、遮光性・遮音性が高い厚手のカーテンがおすすめです。外光や外部音をしっかり遮断できるものを選びましょう。
ただし、朝に自然と目覚めるためには、適度な明るさも必要です。タイマー式のスマートカーテンを取り付けるなど、快適さを高める工夫を考えてみてください。
まとめ

ブラインドとカーテンは、それぞれにメリットもあればデメリットもあるため、一概にどちらがいいとは言い切れません。自分たちがイメージする部屋のテイストや機能、予算などから、どちらが向いているのかを考えてみてください。
しかし、どれだけメリットとデメリットを比較しても、実際に部屋に取り付けたときの雰囲気や使い心地などを完璧にイメージするのはとても難しいと思います。
「自分では決められない」「どの種類にするか悩む」というときには、ぜひリビングサーラの『くらすコンシェル』をご利用ください。
プロの建築家がリノベーションからインテリアまで、お客さまの理想の空間づくりをお手伝いいたします。
▶『くらすコンシェル』の詳細はこちらのページから
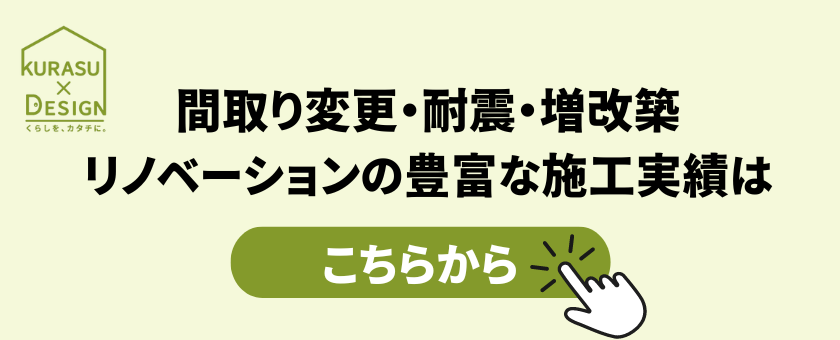
■監修_リビングサーラ/施工管理担当者_資格:1級建築施工管理技士・2級建築士

WRITER PROFILE
建築科系学科卒の住宅×金融専門ライター 井本 ちひろ
子供に「おかえり」が言える仕事を探してライターの道へ。
大学で得た経験とFP2級の知識を活かし、家づくり、水回り設備、エクステリア、火災保険、相続など、住宅にまつわる幅広い記事を中心に活動中。











