お部屋別!床材の種類と選び方まとめ

リフォームをされる際、床材選びは悩むポイントが多くあります。
フローリングやクッションフロアなど、様々な床材がありますが、それぞれに耐水性や遮音性などの機能、デザインや色など、メリットとデメリットが存在します。
好みの見た目の床材になっても、素材によっては滑りやすくなったり、汚れが目立ったりと、機能面での注意点もあり、悩ましいものです。
床材選びには、まずはその部屋やスペースで、何に優先順位をつけるかが重要です。
今回は、普段はくつろぐリビングや寝室などと、水回りとに分けておススメな床材を紹介します。
リフォームの際の床材選びにお悩みでしたら、是非ご参考にしてください。
主な床材の種類
床材は種類に応じて触り心地や模様、色味など、バリエーションも様々です。それぞれの特徴を知り、理想とするリフォームの成功に向けてイメージを高めましょう。
フローリング(無垢・複合)~木材が生み出す温かみ~

多種多様な木材でできているフローリングは、室内に温かみのある雰囲気を生み出します。種類には大きく分けて無垢と複合の2つに分かれます。
それぞれの特徴は以下の通りです。
無垢
天然の一枚板をそのまま加工したもので、材質にはスギやヒノキ、ウォールナット、アカシアなどがあります。水分を発散・吸収する調節作用を持ち、足に温かみを感じられますが、室温の変化で膨張と収縮することで反りや隙間割れする可能性があります。
複合
合板の上に天然木や木目調のシートを張り合わせたもので、材質には厚さ2ミリ程度の挽き板、厚さ0・3〜1ミリの突き板、木目のプリントシートがあります。無垢よりもコストが低く、反りや隙間割れのリスクも少ないですが、木の質感が薄く、傷ができると修復しづらいデメリットがあります。
クッションフロア~踏むと沈むような感触~
塩化ビニル素材でできており、歩くたびに少し沈むような感触があります。耐水性に優れ、コストが安価な上に、簡単に加工できるため狭いスペースでも施工しやすいです。
木目風や大理石風などのバリエーションがあるので、様々なデザインを楽しみたい方におススメですが、安価なものは表面のプリントが剝がれしまうことがあります。
カーペット(絨毯)~種類によって異なる機能~
天然素材や合成繊維で作られており、断熱効果や防音性を持っています。
天然素材には吸湿性・防火性のあるコットンや通気性のあるリネンがあります。
また、合成繊維には防カビ・防虫性に優れたウールやナイロンがあり、どちらも優しい踏み心地があります。
寝転がりやすいですが、ホコリや髪の毛が入り込んだり、飲み物をこぼすとシミになるなどの弱点があります。
フロアタイル~優れた耐久性と耐水性~
タイル状になった塩化ビニル製の床材で、クッションフロアとは違ってクッション性はなく、硬いのが特徴です。耐久性・耐水性が高く、色柄も豊富ですが、クッションフロアに比べるとコストは高めで、割れる恐れもあります。
畳~夏も冬も愛される日本の文化~
和室でお馴染みの畳は柔らかく、さらりとした肌触りが特徴です。断熱性や保湿性に優れ、夏場も冬場も過ごしやすい床材です。畳の独特な香りや、寝転がれる点も好まれる要因の一つです。最近は琉球畳などのモダンな雰囲気を生む畳もありますが、長く太陽光に当たると色が変わってしまう欠点もあります。
コルク~温かみがあり、衝撃が少ない~
弾力性があるため歩いて疲れにくく、転倒しても衝撃が少ないです。吸湿性や保温性に優れ、有機質の材料のため温かみもあります。表面は傷が付かないように塗装されているため、ワインのコルクのように崩れる心配はありません。その一方で、自然素材なので日に当たると色が変わることがあります。
くつろぎ空間に最適な床材

リビングや寝室、子供部屋など、普段から快適にくつろぎたいお部屋の床材は、どんなことを優先するかで選び方が変わってきます。
◆快適性
普段から素足で過ごすか、室内履きで過ごすか
◆デザイン
温かみのある雰囲気にしたい
◆機能性
マンション・アパートに住んでいるため遮音性がある、床暖に対応している商品がある
リビング・ダイニング → フローリング、クッションフロア
家族との団欒を過ごす空間には、天然木の無垢フローリングがお勧めです。湿度をある程度維持できるため、夏はダニ・カビを防止し、冬は喉や肌の乾燥を防ぎます。お掃除は重視されたい場合は、クッションフロアにすればお手入れが水拭きのみとラクラクです。
また、広い空間のため、素材ひとつでイメージが変わります。木目調にすれば温かさやアンティークな雰囲気を生み、グレーやホワイトのモノトーン色はシックな感じを表現します。
寝室 → カーペット、コルク
温かみ、静けさ、足触りの快適さを優先すれば、一晩で疲れも取れやすい寝室になります。素足で過ごす時間が多いため、カーペット(絨毯)であればフカフカした質感はリラックス効果を得られます。寒い冬でも冷えを感じにくいメリットもあります。
部屋の湿度を快適に保てるコルクもお勧めです。適度な弾力や温もりがあるため、寒い時期でも快適な朝を向かえられます。
子供部屋・書斎 → フローリング、カーペット、コルク
お子様が走ったり、転んだりしてもケガをしないように、柔らかい針葉樹(具体的な樹種としては桧・杉・松など)でできたフローリングや、防カビ・防虫性のあるカーペット、遮音性に優れたコルクが最適です。書斎でワークチェアを頻繁に使うのであれば、床が傷つきにくいカーペットがお勧めです。ペットと遊びたいスペースには、滑りにくくて傷がつきにくいコルクがいいでしょう。
水回りに最適な床材

水回りの床材を選ぶ際にも、どんなポイントを重視するかで選ぶ床材は変わってきます。調理や洗濯といった家事をするスペースや、汚れやすい場所も多いため、機能性を重視したい方が多いでしょう。
◆機能性
掃除がしやすい、水に強い、汚れに強い、表面強化
◆デザイン
目地が少ない、清潔に見える、調和が取れている
キッチン → フローリング、クッションフロア、コルク
調理中に水や油が床に跳ねてしまうため、耐水性・防汚機能のある床材がベストです。リビングと仕切りのないアイランドキッチンであれば、防水性のある複合フローリングがお勧めです。色や模様のバリエーションも豊富で、お部屋全体のイメージを損ねる心配もありません。独立したキッチンなら、足腰への負担が少ないクッションフロアが人気です。水拭きもできて掃除も簡単です。耐水塗装がしてあればコルクでも問題ありません。
トイレ・洗面所 → クッションフロア、フロアタイル
防水・防汚性のあるクッションフロアがお勧めです。トイレのような狭い空間でも施工しやすく、重ね張りもできます。アンモニアによるシミ汚れを防ぎ、なかには抗菌・消臭機能が付いた製品もあります。「ホテルのようなおしゃれな質感にしたい」といったデザイン重視の方には、立体感を演出できるフロアタイルもいいでしょう。
脱衣所 → クッションフロア、コルク
濡れた体を拭くため、耐水性が高いクッションフロアや、冬場のヒートショック対策という観点からコルクもお勧めです。
浴室 → ビニル床シート、ストーン、サーモタイル(冷たさを軽減したタイル)
耐水性が高い床材が適しています。耐久性にも優れて傷が残りづらく、掃除も拭き取るだけのメンテナンスでOKです。最近は表面が滑りやすいように加工されたフロアタイルもあります。
最後に
生活スタイルや予算に合った床材を選び、適切なリフォームを実現するためにも、信頼できるリフォーム会社に相談することも大切です。
リビングサーラでは豊富な床材を取りそろえたリフォームにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
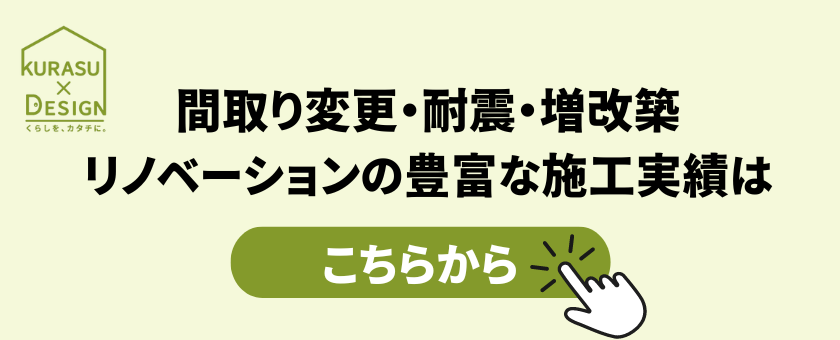
■監修_リビングサーラ/施工管理担当者_資格:1級建築施工管理技士・2級建築士

WRITER PROFILE
由本 裕貴
1983年3月20日、愛知県豊川市生まれ。
御津高校、愛知大学を経て、2005年に日刊スポーツ新聞社入社。プロ野球やサッカー日本代表を担当し、2014年に東愛知新聞社へ転職。2021年からフリーに転向し、翌年から東日新聞ライターとして東三河のニュースや話題を追っている他、スポーツマガジンやオカルト雑誌などでも執筆。豊川商工会議所発行「メセナ」の校正も請け負う。著書に「実は殺ってないんです 豊川市幼児殺害事件」「東三河と戦争 語り継ぐ歴史の痕跡」「訪れたい 東三河の駅」がある。
家族は妻と長男。趣味はスポーツ観戦、都市伝説の探求。











