初心者さんでもできる!パン作りの基本

手作りパンの、焼きたての味と香りは格別です。家族の笑顔が見たくてハンドメイドのパン作りがやめられないと、その魅力を語る人たちがいる一方で、「自分で作ってみたいけど、手作りはハードルが高そう」と二の足を踏んでいる方も多いのでは?
そんなパン作り初心者のみなさん、実は基本さえ押さえれば、初心者でも美味しいパンを作ることができるんです。
このコラムでは、必要な道具と材料、パン作りの工程、コツなどを丁寧に解説します。初心者さんでも美味しく作れるパンの種類もご紹介。あなたもパン作りデビューしてみませんか。
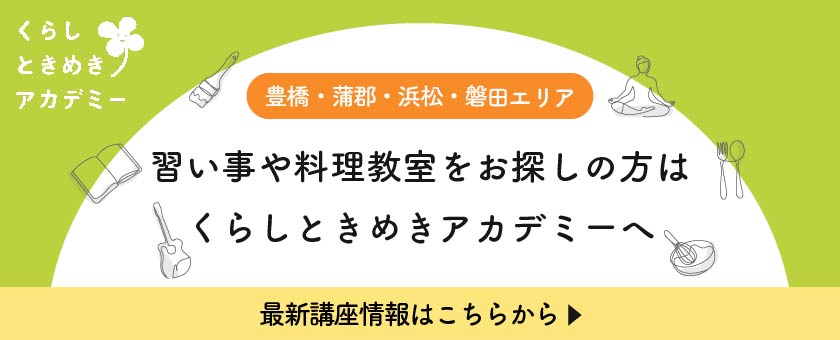
目次
パンは初心者でも手作りできるの?
はい。パン作りは思っているよりずっと簡単です!むしろ始めるのにはピッタリの趣味と言われています。以下にその理由をいくつか挙げてみましょう。
材料がシンプル
強力粉、イースト、塩、砂糖、水があれば基本的なパンは作れます!スーパーで簡単に手に入る身近な材料ばかりですね。
道具も最小限
ボウル、計量カップ、オーブンなど少しの道具で始められます。ホームベーカリーを使えばさらに簡単に焼けます。
失敗しても大丈夫
パン作りは、多少失敗してもおおむね美味しく食べられます。それに、失敗を重ねることで上達する楽しみがあります。
レシピが豊富
インターネットで初心者向けレシピが無料で見つかります。動画で手順を確認できるものも多数あります。さらに、手軽に習えるパン教室も豊富です。
達成感がすごい
自分で作ったパンの香りと味は格別。家族や友人、恋人などに振る舞えて喜ばれます。
応用が効く
基本の作り方に慣れてきたら具材を変えたり形を変えたり、パン作りは自由自在。クリエイティブな楽しみ方もできそうです。
作業は多少手間はかかりますが、基本さえ理解すれば決して難しいものではありません。むしろ材料を混ぜてこねる、生地を発酵させるなど、一つひとつの工程を丁寧にこなすことが美味しいパン作りにつながります。初心者でも焼きたての美味しいパンを味わう感動を体験できるはずです。最初は失敗を恐れずチャレンジすることが大切ですね。

パン作りに必要な道具と基本的な材料
パン作りの基本の道具
【必須の道具】
◆ボウル
ボウルはパン生地を混ぜるための基本的な道具です。ステンレス製とガラス製のボウルが一般的に使用されます。ステンレス製ボウルは耐久性が高く、熱伝導が良いため、温かい材料を扱う際にも適しています。ガラス製ボウルは目視で混ぜ具合を確認しやすく、電子レンジでの使用にも便利です。ボウルのサイズは、作るパンの量に応じて選ぶことが重要です。
◆計量道具
正確な計量はパン作りの成功に不可欠です。デジタルスケールはグラム単位での計量が可能で、材料の微細な差異を正確に測ることができます。とくに、酵母や塩などの少量の材料は、正確な計量がパンの発酵や味に大きく影響します。液体の計量には目盛りがついた計量カップが便利で、ミリリットルやカップ単位での計量が可能なものを選ぶと、さまざまなレシピに対応できます。また計量スプーンは、粉末材料の計量に使用。深くて口の狭いものを選ぶと、すり切りがしやすくて便利です。
◆こね台
こね台は生地をこねるための平らな作業台で、木製やシリコン製のものがあります。木製は伝統的なパン作りに適しており、しっかりとした感触で生地を扱うことができます。シリコン製こね台は滑りにくく、洗浄も簡単。こね台の選び方は、使用する生地の種類や量に応じて決めると良いでしょう。
◆オーブン
オーブンはパンを焼くために欠かせない道具です。温度調整がしやすいオーブンを選ぶことで、焼き加減をコントロールしやすくなります。パンの種類によっては、トースターやフライパンで代用できることもあります。
【その他の基本道具】
◆スケッパーとカード(ドレッジ)
スケッパーはパン生地を寄せ集めたり、分割したりする時に使います。プラスチック製でやわらかいタイプが便利です。カード(ドレッジ)はパン生地を分割する時や、ボードやボウルにくっついたパン生地を剥がす際に使用します。樹脂製のカードは安全で、保存容器や捏ね板を傷つけない利点があります。
◆めん棒
めん棒は生地をのばす時に使います。長いめん棒は生地を大きくのばす成形の際に便利。またガス抜きめん棒を使えば、生地を均一にのばしながらガス抜きをすることが可能です。
◆温度計
仕込み水の温度が高すぎるとイースト菌が死滅する可能性があるため、温度計で温度を測ることがあります。
◆パンマット
パンマットはベンチタイムで生地を休ませる時や、バゲットなどを布取り発酵させる時に使用します。水分をうまくコントロールしてくれるため、ベタつく生地でも手粉を最小限に抑えることができます。
◆クッキングシート
クッキングシートは発酵時に必要で、パン生地を成形した後、クッキングシートを敷いた天板に生地を載せて発酵させます。アルミホイルだと生地がくっついてしまうため、クッキングシートを使うのがおすすめです。
今は100均などでも、手軽に製菓道具が手に入るようになりました。できるだけ活用し、節約しつつ美味しいパンが作れたらベストですね。

初心者向けの材料
おもな材料は、強力粉、イースト、塩、砂糖、水、砂糖などです。
パン作りにおいて、強力粉は最も重要な基本の材料です。小麦粉の中でも強力粉はグルテンが豊富で、パンに必要な弾力性と構造を提供します。
イーストは、パン生地を発酵させるために欠かせない材料です。とくにドライイーストは、保存が効き、扱いやすいため初心者に最適です。ドライイーストは水分と温度に敏感で、適切な条件下で活性化されます。生地に加える際は、温かい水と混ぜてから使用することで、イーストがしっかりと発酵を始めることができます。発酵の過程は、パンの風味や食感に大きな影響を与えるため、注意深く行うことが重要です。
塩は、パンの味を引き締めるために必要不可欠な材料です。適量の塩を加えることで、パンの風味が増し、イーストの発酵をコントロールする役割も果たします。水は、生地をまとめるために必要で、イーストの活性化に影響を与えるため、一般的にはぬるま湯(約30〜40度)が推奨されます。
砂糖は、イーストの発酵を助けるために少量使用されます。砂糖はイーストの栄養源となり、発酵を促進することで、パンのふんわりとした食感を生み出します。とくに、甘いパンや菓子パンを作る際には、砂糖の量を増やすことが一般的です。ただし、砂糖の量が多すぎると、逆に発酵が妨げられることもあるため、レシピに従って適切な量を使用することが重要です。

パン作りの流れと初心者向けのパン
パン作りの基本的な流れ
材料を計量する(約5分)→混ぜ合わせ生地をこねる(約20分)→生地を発酵させる(1次発酵・約60分)→ガス抜きをして分割する(約5分)→生地を丸めて整形し、型やトレーに並べてベンチタイムを置く(約10分)→二次発酵をさせる(約60分)→焼成する(約15分) ※時間は、おおよその目安です。
パン作りは、生地作りと発酵、焼成という大きな3つの工程に分けられ、この工程を経て美味しいパンが完成します。決められている時間や分量をしっかりと守ることが重要です。
初心者向けのパン
基本の丸パン:シンプルな味わいのふんわりしたパンで、ドライフルーツやチョコチップなどを混ぜ込んだり、あんこやクリームといったフィリングを包むなどアレンジもできます。
フォカッチャ:もっちりとしたイタリアの食事パンです。こねる必要がないので簡単。バターではなくオリーブオイルを使うことで、イタリアンらしさが出ます。ローズマリーで風味付けしますが、お好みでオリーブを載せても美味しいです。
ピザ:トマトソース、チーズ、バジルのマルゲリータが基本ですが、お好きなトッピングを追加したり、トマトソースをホワイトソースやカレーソース、和風ソースに変えるなど幅広く楽しめます。
豆乳ブレッド:水や牛乳の代わりに豆乳を使用し、30分で作れる手軽さが魅力です。イーストを使わずに作るため、すぐに焼き上げられます。

失敗しがちなポイント
初心者が失敗しがちなのは「こねすぎ」や「発酵不足・発酵しすぎ」です。
こねすぎると、パンがパサついたり硬くなってしまいます。生地がまとまり、ツルツルしてきたら速やかにこね上げるのがコツ。こねる時間の目安は10~15分程度です。
発酵は生地の様子を見ながら調整することが大切。生地が約2倍に膨らんだ頃が発酵完了の目安です。室温や材料の温度で発酵時間は変わるので、レシピ通りの時間にこだわらず生地の様子を見極めましょう。
まとめ
パン作りは、最初は失敗を気にせずチャレンジすることが何より大切。一つひとつの工程を丁寧にこなし、生地の様子を観察することを心がけましょう。
道具や材料は最低限のものから揃え、まずはシンプルな配合のパンに挑戦してみてください。何度も作るうちにコツをつかみ、美味しいパンが作れるようになっていくはずです。
ちょっとしたコツやアドバイス、アレンジの仕方などを知りたい方はパン作りの講座を受講するのがおすすめです。まずは体験講座や単発講座に参加してみてはいかがですか。
くらしときめきアカデミーでは、ガスオーブンを使ったパン作りの単回講座を多数開講しています。レベル感も初心者向けから上級者向けまで取り揃えていますので、ぜひ自分に合った講座を探してみてください。
焼きたての香りと優しい味に、手作りパンのとりこになること間違いなしです。
参照:くらしときめきアカデミー
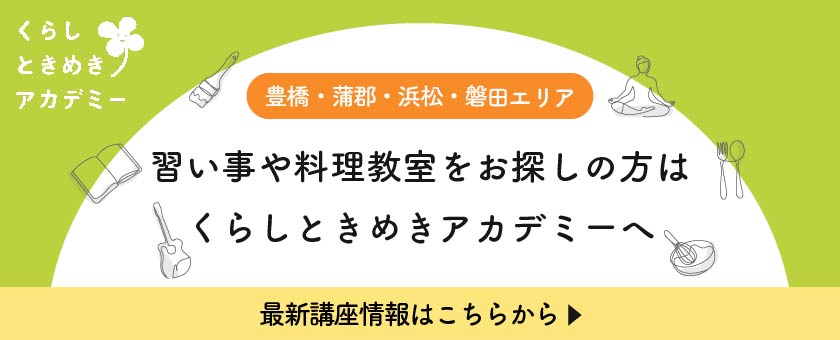
■監修_サーラエナジー/アカデミー担当者

WRITER PROFILE
書こ音(かこね)ライティング 森 美香
元地方新聞社報道記者。
企業事務、医療事務、 英会話インストラクター など、さまざまな職種を経験。 記者を経て、現在は、自分史・社史関連、 行政、 観光協会、 企業、 雑誌などでフリーライターとして活動中。
一般社団法人自分史活用推進委員会認定・自分史活用アド バイザー。











