退職金のもらい方は?「一時金」と「年金」どちらがお得?
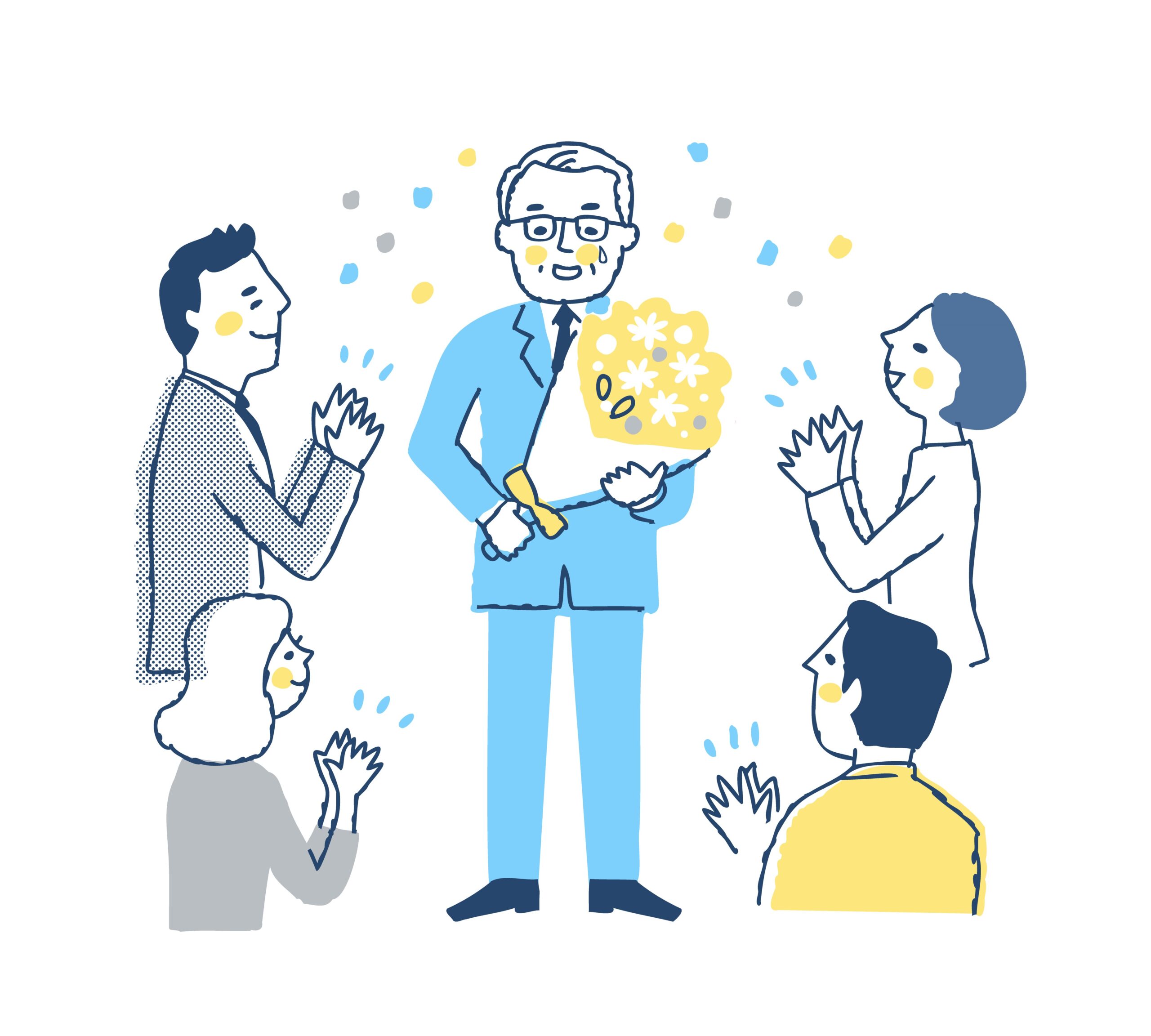
会社を退職するときにもらえる退職金。正しいもらい方を知らないと損をしてしまうかも。ここでは、退職金のもらい方の種類やメリット・デメリット、退職金にかかる税金についてご説明していきます。
(※ここでは企業年金制度がある前提での内容になります。)
退職金のもらい方の種類

退職金のもらい方には「一時金」と「年金」の2つがあります。
一度に全部もらう方法が「一時金」、分割してもらう方法が「年金」です。
この2つは受け取りにかかる税金が異なります。
一時金でもらった場合には退職所得として所得税・住民税の課税対象となり、年金の場合には雑所得として所得税・住民税の課税対象となります。
それぞれのメリット・デメリットを知り、定年後のライフスタイルに合わせたおトクなもらい方を見つけましょう。
一時金でもらうメリット・デメリット
退職時にまとまった金額を一括で受け取る方法です。
〈メリット〉税金面の優遇が大きい
退職金を一時金としてもらう場合のメリットは、税負担が軽くなることです。
通常、所得には税金が課せられますが、退職金を一時金でもらった場合は「退職所得」となり、税制上の優遇があります。
退職所得控除額は、勤続年数が長いほど増えます。
具体的には次のように計算された「退職所得」が所得税、住民税の対象となります。
退職所得=(退職金-退職所得控除額)×1/2
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
| 20年以下 | 40万円×勤続年数 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
退職所得控除の範囲内であれば、税金はかかりません。
例えば勤続年数が43年の場合、退職所得控除は2,410万円となりますので、退職金が2,410万円以下なら課税対象とはなりません。
退職所得控除を超えた分は課税対象になりますが、課税対象となるのは退職所得の2分の1、さらに給与所得等の他の所得とは合算せずに税率が計算されます(分離課税)。
まとまったお金をもらうことで住宅ローンの繰り上げ返済や大きなライフイベントに対応ができます。
〈デメリット〉退職年金に比べ受取総額が少なくなる
受取総額は通常、退職年金より少なくなります。
退職年金の場合は、まだもらっていない退職金を金融機関側が運用するため、受取額が増えるのが一般的です。
なお、年金で受け取るよりも受取金額の総額は少なくなりますが、自分でうまく運用できれば年金受け取りよりも受取総額を増やすことも可能です。
年金でもらうメリット・デメリット
退職時退職金を年金のように分割して受け取る方法です。
〈メリット〉一時金よりも受取総額が多い
退職金の運用益が上乗せされるため、受取総額がアップする可能性があります。
長期での受け取りを選ぶほど、受取総額が増える可能性は高まっていきます。
→まとまった一時金を自身で管理するより、定期的な収入とする方が安定した生活を送ることができます。
〈デメリット〉税負担が発生する可能性が高い・給付の減額の可能性
年金受取は税負担額が高くなる恐れがあります。
一時金として支払われる退職金であれば、「退職所得」に対する税制上の優遇措置がありますが、退職年金には「公的年金等控除」という制度が適用されます。
これは厚生年金と合算されて計算されるため、一時金に比べ税負担が大きくなるのが一般的です。
また、定年後の会社の業績が低迷した場合、給付額が減少する場合があります。
所得の計算方法と公的年金等控除の規定は以下の通りです。
【雑所得金額の計算】
雑所得=(a)収入金額の合計額×(b)割合-(c)公的年金等控除額
〈65歳未満〉
| (a)収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)公的年金等控除額 |
| 70万円以下 | – | – |
| 70万円超~130万円未満 | 100% | 70万円 |
| 130万円~410万円未満 | 75% | 37万5,000円 |
| 410万円~770万円未満 | 85% | 78万5,000円 |
| 770万円以上 | 95% | 155万5,000円 |
〈65歳以上〉
| (a)収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)公的年金等控除額 |
| 120万円以下 | – | – |
| 120万円超~330万円未満 | 100% | 120万円 |
| 330万円~410万円未満 | 75% | 37万5,000円 |
| 410万円~770万円未満 | 85% | 78万5,000円 |
| 770万円以上 | 95% | 155万5,000円 |
退職金をもらったら確定申告は必要?
退職金を受け取った場合、通常は確定申告の必要がありません。退職金は、会社が支払う際に「退職所得の源泉徴収票」を基に税金を計算し、天引きして納税手続きを完了しています。この仕組みにより、受け取る本人が確定申告をする必要が基本的にはありません。
ただし、他の所得がある場合や特定の控除を受ける場合は申告が必要です。不安な場合は、税務署や税理士に相談すると安心です。

退職金をもらう際の注意点

退職金は人生の中で大きな金額を受け取る機会の一つです。そのため、適切に管理し、将来の生活を支える資金として活用することが大切です。以下に、退職金をもらう際の注意点をまとめました。
自己都合退職の場合、満額支給されない場合がある
自己都合退職の場合、退職金が満額支給されないケースがあります。これは、会社の退職金規定や就業規則によるもので、退職の理由や勤続年数によって支給額が変動する仕組みになってるため、企業によって条件は異なります。退職前に退職金規定をしっかり確認し、自身の状況に応じた最善の選択をすることが重要です。
老後について検討してからもらい方を決める
退職金は老後の生活を支える重要な資金です。老後の生活設計を具体的にイメージし、一括受け取りや分割受け取りのメリット・デメリットを比較したうえで、自分に合った方法を選びましょう。
また、生活スタイルに合った使い方を考えるため、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。無駄のない計画で、安心した老後を迎えましょう。
お金に関するお悩みがある方は、ぜひサーラフィナンシャルサービスへお問合せください。
税控除を活用した節税のコツ
「一時金」と「年金」、どちらがいいのか迷ったらまずは自分の勤続年数から一時金でもらう場合に受けられる退職所得控除額を算出してみましょう。
退職金が退職所得控除の控除対象に収まっていれば、全額一時金受け取りが最適といえます。
しかし、退職所得控除に収まらない場合は、収まる範囲だけ一時金でもらい、残りは『年金』でもらうのがいいでしょう。
それぞれの状況に応じて、「一時金」と「年金」を併用するなど、最善の受取方法を見つけてください。
退職金のもらい方についてよくある質問

退職金のもらい方についてよくある質問をまとめました。
退職金は前払いできる?
退職金の前払いは、企業によって可能な場合もありますが、制度の有無や条件に依存します。前払いを希望する際は、まず会社の人事部門に相談し、規定や手続きについて確認しましょう。
退職金をもらうための最低勤務年数はどのくらい?
退職金をもらうための最低勤務年数は企業や業種によって異なりますが、一般的には3〜5年程度が目安です。退職金制度がある場合は、事前に就業規則を確認し、自身の勤務状況が条件に合致しているかを確認することが大切です。また、自己都合退職や会社都合退職で支給条件が変わる場合があるため、退職理由も考慮しましょう。
まとめ

退職金のもらい方には、一時金(まとめてもらう)と年金(毎月に分けてもらう)ふたつの方法があります。
控除の優遇を考えると一般的には一時金としてもらった方がお得といえますが、場合によっては年金でもらった方がよいこともあります。
退職金の受け取り方を判断するには、老後資金がどの程度貯まっているのか、退職後も働くのかなど、様々な要因が絡んできます。
また、一時金で受け取った場合に自分でどの程度の利回りで運用できるかによっても最終的な選択は異なります。
それぞれの控除額を計算してみたり、自身の定年後のライフスタイルを想像してみたりして、自分に合った最もおトクなもらい方を選択していきましょう。

■監修_サーラフィナンシャルサービス/担当者_資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士












