火災保険と地震保険は控除される?節税・節約のポイントを解説!

そろそろ年末調整の時期。
今年マイホームを購入した方や新たに火災保険と地震保険に加入した方は「控除の対象になる?」と、疑問に思っていませんか?
結論からお伝えすると、控除が受けられるのは地震保険のみです。
どういった仕組みで、どのくらいの控除が受けられるのでしょうか。
そこで本記事では、控除の仕組みや手続きの流れ、保険料の負担を少しでも減らす方法を解説します。ぜひ参考にしてください。
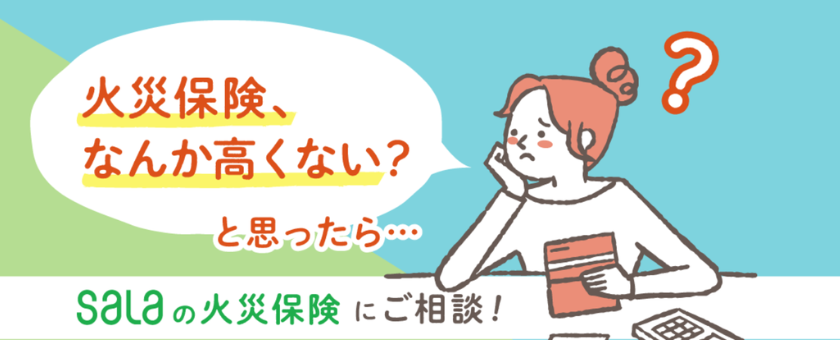
目次
火災保険は控除の対象にならない!

冒頭でもお伝えしたように、年末調整や確定申告時に控除が受けられるのは地震保険のみ。火災保険は控除の対象とはなりません。
かつては火災保険で10年以上の長期契約を対象にした『長期損害保険料控除』がありましたが、2006年(平成18年)に廃止されています。
地震保険料控除の仕組み

長期損害保険料控除が廃止されたあと、地震保険への加入を促すために創設されたのが、『地震保険料控除制度』です。この制度では、地震保険料から所得税と住民税が一定額控除されます。控除の仕組みと条件を見ていきましょう。
所得税と住民税から一定額が控除される
地震保険料控除制度では、支払った地震保険料から控除額が決まります。
| 年間支払保険料 | 控除額 | |
| 所得税 | 50,000円以下 | 支払保険料 |
| 50,000円超 | 50,000円 | |
| 住民税 | 50,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 |
| 50,000円超 | 25,000円 |
※2007年(平成19年)1月1日以降の契約
たとえば年間4万円の地震保険料を支払っているなら、所得税は4万円、住民税は2万円が控除されるため、合計で6万円の節税効果が得られるという計算になります。
一方、年間6万円を払っている場合は、所得税5万円、住民税25,000円と、上限額までしか控除されません。
保険料によっては全額控除されない、という点を覚えておきましょう。
また、所得税は確定申告や年末調整時に反映されますが、住民税は翌年5〜6月頃に届く『住民税決定通知書』でわかるため、それぞれタイミングが異なります。
参考:国税庁『No.1145 地震保険料控除』
控除を受けるための条件
地震保険料控除制度を受けるためには、次のような条件を満たす必要があります。
- 地震への損害を対象にした保険であること
- 納税者本人が契約者であること
- 常に居住用として使用される建物、家財のために契約していること
- 建物や家財の所有者が、契約者または契約者と生計同一の配偶者・親族であること
- 地震保険料を実際に払い込んでいること
これらの中でとくに注意したいのが、「保険料の支払いについて」です。
保険料が未納であったり、口座引き落としが完了していなかったりすると、控除対象外となってしまいます。払い込みが完了しているか、必ず確認しておきましょう。
地震保険料控除を受けるための手続き
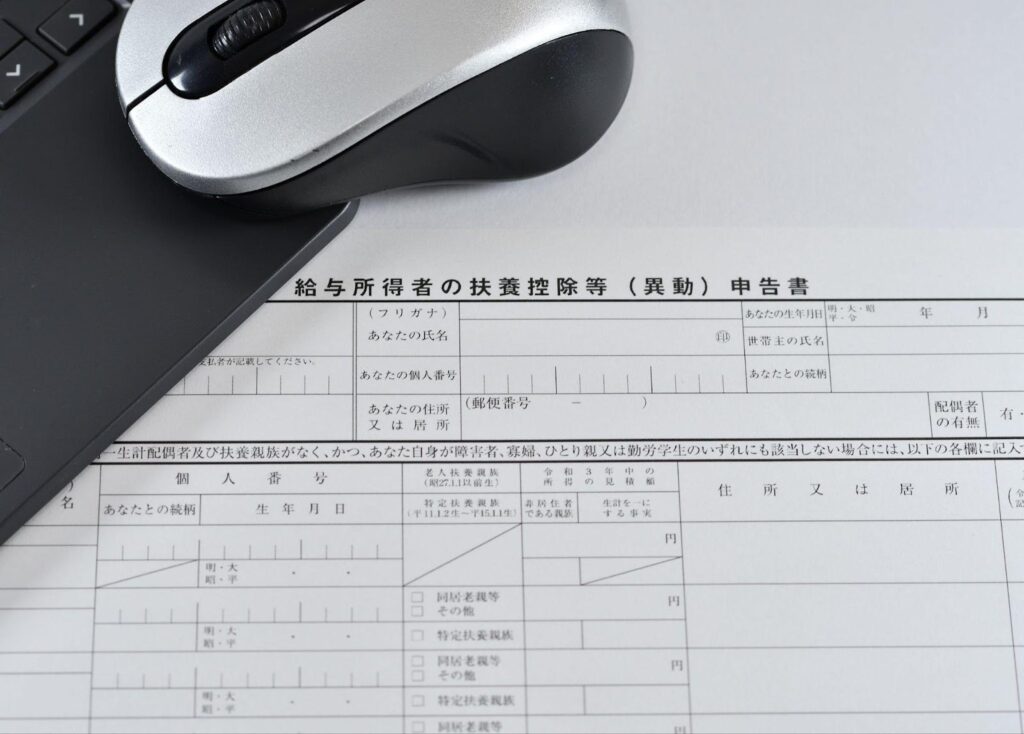
地震保険料は、勝手に控除されるわけではありません。
会社員などで給与所得がある人は年末調整時に、自営業や医療費控除などで確定申告を行う人はその際に手続きを行います。それぞれの方法を見てみましょう。
会社員などで年末調整を受ける人
会社勤めで年末調整を受ける人は、10月ごろに届く『地震保険料控除証明書』を勤務先に提出するだけで手続きは完了です。年末調整で自動的に所得税の控除が反映され、住民税は翌年春頃に反映されます。なお、契約初年度については保険証券に地震保険料控除証明書が付属されていることもあるため、大切に保管しておきましょう。
なお、紛失した場合は保険会社に問い合わせれば再発行してもらえますが、年末調整の期限に間に合わないと確定申告が必要になる可能性があるため注意が必要です。
確定申告が必要な人
確定申告が必要な人は、その際に地震保険料控除を申告することで所得税と住民税の控除を受けられます。申告が必要になるのは、主に次のような人です。
- 個人事業主などで48万円を超える事業収入がある人
- 年収が2,000万円を超える給与所得者
- 副業などで本業以外の所得が年間20万円を超える人
- 医療費控除を受ける人
- 住宅ローン控除初年度の人
年末調整と同様に、申告時には地震保険料控除証明書が必要です。
確定申告は申告期限があり、土日祝が絡まなければ例年2月16日から3月15日までとなっています。期限を過ぎても5年間はさかのぼって申告できますが、早めの手続きを心がけましょう。
控除よりも効果があるのは『保険の見直し』
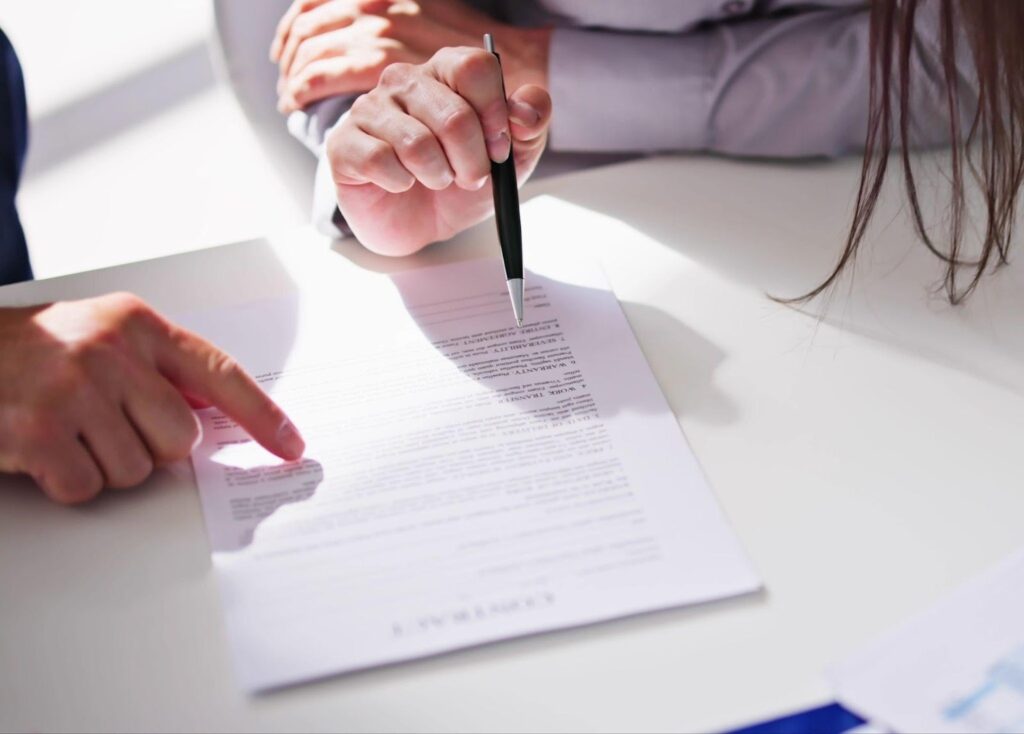
ここまで説明したように、火災保険料は控除対象外です。
地震保険料は控除対象となりますが、それでも控除額は所得税と住民税を合わせても最大で7.5万円と、限られています。もし「少しでも家計への負担を減らしたい」と考えているなら、保険の見直しが効果的です。
火災保険・地震保険を見直したほうがいいケース
火災保険と地震保険を見直したほうがいいのは、次のような方です。
- 補償内容が不足している
- 付帯したい特約がある
- 保険料が高く、家計の負担になっている
- 契約から10年以上見直しをしていない
火災保険は補償範囲や料金、特約などが保険会社ごとにさまざま。定期的に見直さなければ、住宅の状況などに見合っていないケースも出てきます。
また、特約の存在を知らずに契約してしまった場合も、災害や事故が起こったときに腹を切ることになります。とくに小さなお子さんがいるご家庭なら『破損・汚損』や、『個人賠償責任保険』があったほうが安心です。
【Point!】火災保険の特約、『破損・汚損』『個人賠償責任保険』とは?
破損・汚損は、不測かつ突発的な事故が起こったときに補償が受けられる保険です。たとえば小さなお子さんがテレビに物を投げて壊してしまったときや、掃除中に壁に物をぶつけて壁が凹んでしまったときなどに、保険料が支払われます。
個人賠償責任保険は、他人にケガをさせたり物を壊したりしたときに、その賠償金が補償される保険です。たとえば、お店で購入前の商品を壊してしまったときや、自転車で通行人とぶつかってしまったときなどに生じた損害賠償責任が補償されます。
【関連記事】火災保険の個人賠償責任保険はどんな補償?
見直しで得られるメリット
火災保険・地震保険の見直しには、次のようなメリットがあります。
- 自宅や自分たちに合う補償内容に切り替えられる
- 保険料が下がる可能性がある
前述のように、火災保険の内容や料金などは保険会社によってさまざまです。
保険内容の見直しには、自宅や自分たちの状況に合ったものへと切り替えられるというメリットがあります。
さらに、より補償が手厚く保険料が低い会社を見つければ、家計の負担軽減にもつながります。
地震保険料に関してはどの会社でも同じですが、火災保険は数万円単位で保険料を抑えられる可能性があるので、「保険料の負担が重い」と感じているなら見直しを検討しましょう。
【Point!】火災保険は途中解約ができる!
長期契約などで保険期間の途中であっても、火災保険は途中解約が可能です。未経過期間に応じた解約返戻金が戻ってくる可能性があります。
解約手続きは保険会社または代理店に連絡して行い、保険の空白期間ができないよう、解約手続きの前に新しい火災保険・地震保険に加入しておきましょう。
まとめ

火災保険料は控除の対象外ですが、地震保険料は年末調整時または確定申告によって申告すれば、一定額まで控除されます。スムーズに手続きを行うためにも、『地震保険料控除証明書』を必ず手元に用意しておきましょう。
また、保険料の負担を抑えたい方は、控除よりも保険の見直しが効果的です。
サーラフィナンシャルサービスでは、お客さまの家族構成やご自宅の築年数・状況などから最適な保険をご提案いたします。
解約や新規契約の手続きなどのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
▶サーラフィナンシャルサービスができること
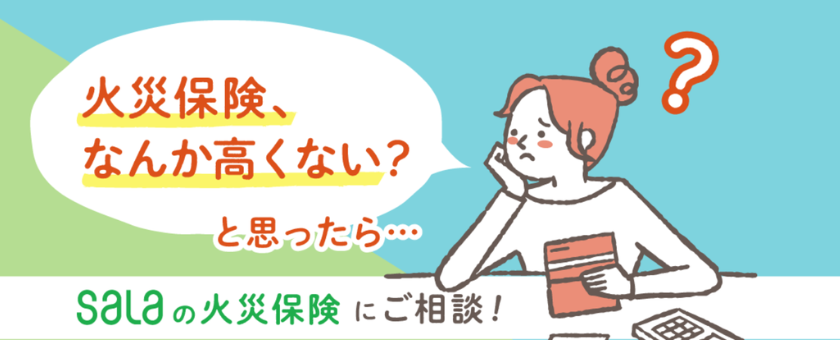
■監修_サーラフィナンシャルサービス/担当者_資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士

WRITER PROFILE
建築科系学科卒の住宅×金融専門ライター 井本 ちひろ
子供に「おかえり」が言える仕事を探してライターの道へ。
大学で得た経験とFP2級の知識を活かし、家づくり、水回り設備、エクステリア、火災保険、相続など、住宅にまつわる幅広い記事を中心に活動中。











